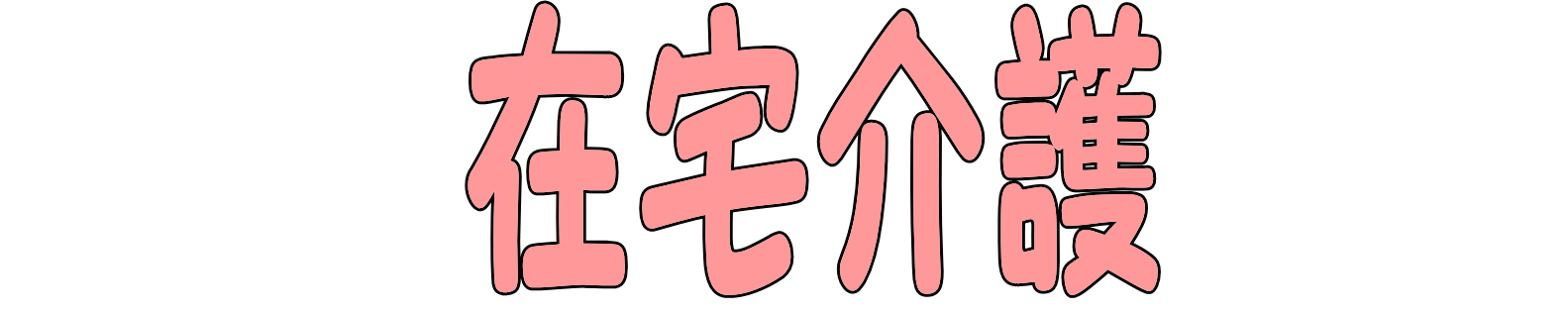高齢者の睡眠障害と健康リスク

睡眠に関する問題は、高齢者になるほど真剣に向き合うべき重要なテーマであり、年齢を重ねるにつれ、睡眠の質やパターンが変化し、健康に大きく影響が生じることが知られています。また、高齢者においては、睡眠時間が短くなりがちで、中途覚醒や不眠症などの睡眠障害に悩まされる方が多いようですね。
在宅介護の母は、とにかくよく寝ます。朝食と昼食後は必ずベッドで寝ますし、夜の就寝も早いほうだと思います。しかし、ここ2年くらいは朝起きる時間が遅くなり、私が家にいるようになってからは、起こさないと何時までも寝ているような状態です。
果たしてこのままで良いのか?高齢者にとっての睡眠とは何かを、考えてみたいと思います。
高齢者の睡眠時間が短くなる理由とは
高齢者の睡眠
高齢者は、加齢とともに睡眠が浅くなる傾向があり、高齢者に多い疾患の影響も伴い、不眠や睡眠障害がみられやすくなります。加齢による体内時計の変化によって睡眠に係る体温やホルモン分泌などの生体機能リズムが早い時間にずれ、高齢者は若年者に比べて早寝早起きになる傾向があります。また、高齢者は深い眠りのノンレム睡眠の時間が減り、浅いレム睡眠の時間が増えます。睡眠中の途中覚醒も多くなり、全体的に浅い眠りとなります
高齢者は、一般的に浅い睡眠になることが多いようですね。私自身も60歳を過ぎてからは、眠りが浅くなったようで、よく夢を見るようになりました。トレイに起きるのは、1回あるかないか程度ですね。
母の場合は、90歳くらいまでは朝5時くらいには起床して、朝食と弁当を作ってくれていました。しかし、大変だろうと思って朝食も昼食も外食にしてから、朝は起きてこなくなったような気がします。そういう、生活環境によって睡眠の質が変わったりすることがあるのでしょうか。
高齢者における昼寝の影響について
年齢に限らず、昼寝については「良い習慣」とされることがあります。しかし、高齢者の場合は家にいる時間が長くなるので、昼寝や少しの仮眠が多くなるような気がします。母も、朝1時間と昼に2時間ほど眠ってしまいますが「1時間以上の睡眠は認知症のリスクが上がる」という記事もみられますので心配にはなりますね。今のところ大きな影響はないように思えますが、これからは睡眠の見守りも大切だと感じます。
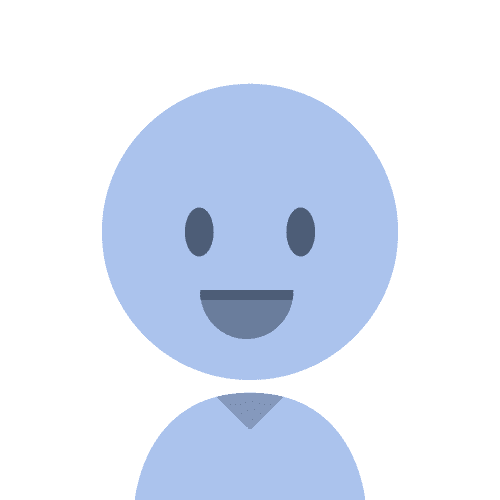
もう90代半ばなので、活動エネルギーが減少しているのかな?もう少し体を動かす習慣を身につけてもらうようにしよう。

PR
高齢者に多い睡眠障害について
どんな睡眠障害があるの?
高齢者では退職・死別・独居などの心理的なストレスに加えて、不活発でメリハリのない日常生活、こころやからだの病気、その治療薬の副作用などによって、不眠症をはじめとするさまざまな睡眠障害にかかりやすくなります。狭心症や心筋梗塞による夜間の胸苦しさ、前立腺肥大による頻尿、皮膚掻痒症によるかゆみ、関節リウマチによる痛みなどによる不眠などキリがありません。またそれらの治療薬によっても不眠・日中の眠気・夜間の異常行動などの睡眠障害が生じます。
また、高齢者がかかりやすい睡眠障害があります。
睡眠時無呼吸症候群
眠り出すと呼吸が止まってしまうため、過眠や高血圧などを引き起こす病気。
レストレスレッグス症候群 / むずむず脚症候群
夜になると出現する下肢を中心とした異常感覚により不眠、過眠を引き起こす病気。
周期性四肢運動障害
睡眠中に、四肢(主に下肢)の筋肉が急速に収縮しては弛緩する不随意運動(ミオクローヌス)が繰り返し起こり、深い眠りが妨げられ中途覚醒が増加します。
レム睡眠行動障害
睡眠中に夢体験と同じ行動をとってしまう病気。
尚、これらの睡眠障害がみられる場合は、専門施設での検査と診断が必要です。
出典:「厚生労働省e-ヘルスネット 高齢者の睡眠」榎本みのり(独立行政法人 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所)
認知症と高齢者の睡眠障害の関係
認知症になると、少なくとも、認知機能が低下して体内時計がおかしくなり、睡眠への影響が大きくなると思います。母が認知症になったときは、夜中に突然起きてきて食事の準備をしたり、出かける用意をすることもありましたね。

高齢者の睡眠を改善するためには?
高齢になると活動量が減ってしまい、昼寝やソファで寝入ってしまうことが多くなりますので、家族の人がある程度は、見守ってあげることが大切だと思います。母を見ていて、日中の活動量との関係から、睡眠の質をよくすることを考えてみました。
規則正しい生活リズム
高齢者の場合は、家にいる時間が長く、ウトウトしたり横になったりする時間が長くなることがあります。できるだけ決まった時間に起床して、食事や入浴の時間も決めておけば、体内時計のリズムがよくなるのではないでしょうか。
最近は、生活リズムをよくするために、少しの時間でも一緒に外に出て歩いたり、景色を見て会話が多くなるように心がけています。
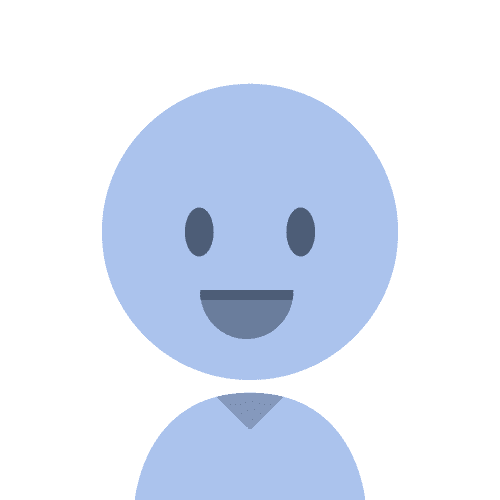
母も、私が家で在宅介護をするようになってからは、食事時間のリズムが良くなったのか、便通が改善されたようです。
刺激物やカフェインの接種を控える
母はお酒も飲まなくて辛いものが嫌いなのですが、コーヒーが大好きなので飲みすぎないように言っています。特に、寝る前数時間の間は、コーヒーや緑茶は飲まないようにしていますが、睡眠への効果がどの程度に改善されるか見守っていきたいと思います。
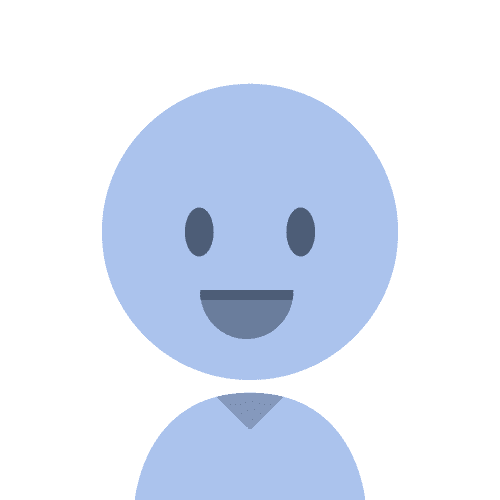
私の場合は、寝る前にプロテインを飲んでいますが、それはどうなんでしょうか・・・
ベッドや枕が合っているか
ベッドのマットレスは、人によって合わないことが多いと聞きますので、まずは本人に合った寝具を選んでみてはいかがでしょうか。母の場合も「枕が高くて寝がえりがうまく出来てないのでは」と言われて、色々ためして今は満足しているようです。
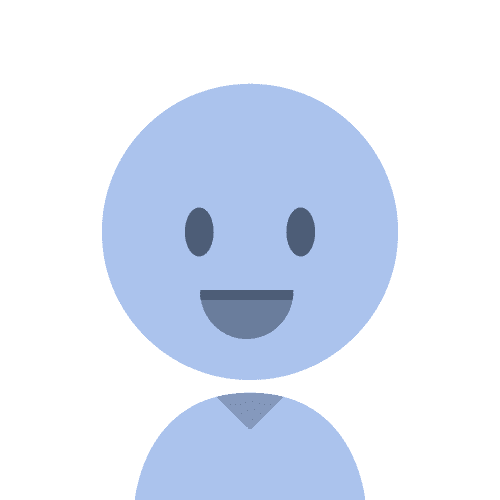
母は、寝すぎることが多いので、合いすぎても困るかも・・・
人生の3分の1が睡眠
きちんと睡眠をとれば、人生の3分の1は睡眠時間であると言われていますね。しかし、最近では「ショートスリーパー」などの言葉があるように、睡眠への考え方が多様になってきたことは間違いないと思います。ただ、それが本当に健康への影響がないのかどうか、すぐに答えが出ないので、真似をすることだけは、やめたほうが良いでしょう。
また、社会生活の中では、夜勤や早朝からの仕事で、睡眠への取り組みが十分に出来ない人もたくさんいると思いますが、それぞれの生活の中ででリズムが取れていれば問題はないのか、考えさせられることではありますね。
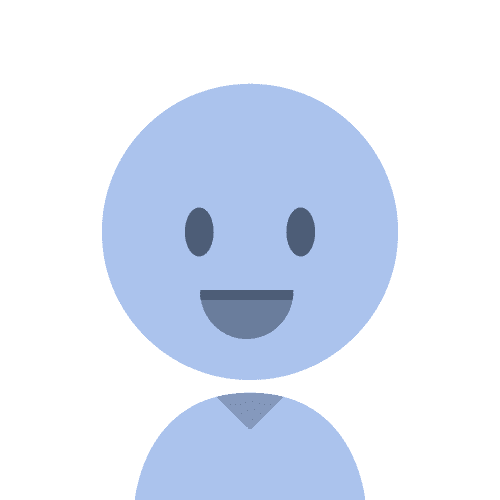
少なくとも若い時と現在では、睡眠に対する体の反応が全く違うことは間違いないと感じています。