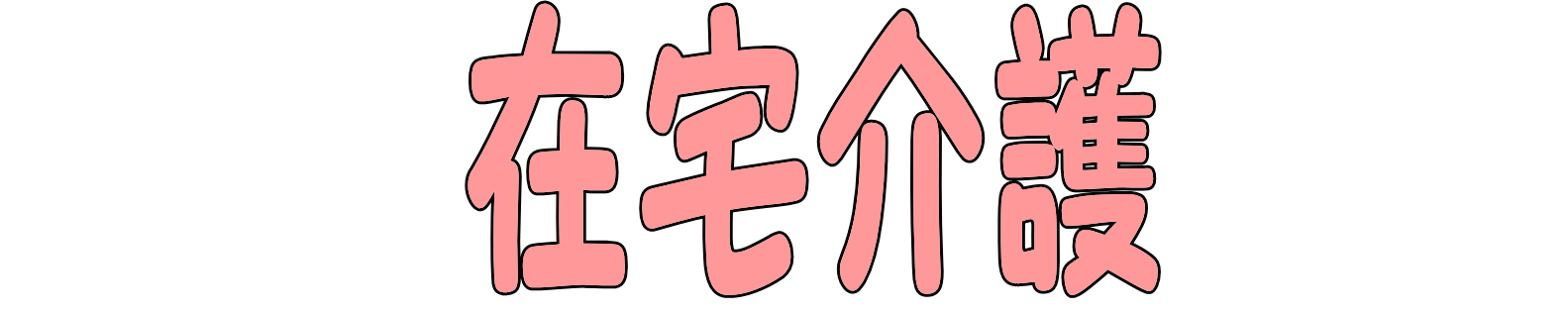介護における高齢者の住宅事情

近年、人口の高齢化が進む中で、「高齢者住宅」の需要はますます高まっています。高齢になると住まいに求める環境や条件が変わり、身体の変化や生活スタイルに合わせて暮らしやすい住宅を選ぶことが重要になるでしょう。持ち家、民営・公営賃貸住宅やシニア向け賃貸住宅など様々ですが、近年は「サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)」にも注目が集まっています。
家族構成により住宅事情は大きく変わってきますが、人生100年時代と言われる中で「住まいの悩み」は、高齢になるほどシビアになってくることは、間違いないでしょう。在宅介護の我が家も、90代半ばの母が階段のある家で住んでいることもあり、将来的に考えなければいけない問題でもあります。
高齢者の住宅選び
持ち家に住み続ける場合の考え方
シニア世代で持ち家に住み続けるメリットは、将来への安心感があり、年金生活者にとっては強みであることはありますね。一方デメリットとしては、家が経年劣化で傷んできた場合には、自分で補修費用を捻出しなければいけないことや、大きな災害などで家に損害が出たときには、最悪の場合、住めなくなってしまうこともあるかも知れません。
また、若い時には必要ではなかった「スロープ」や「手摺」など、バリアフリーに思わぬ出費が出てしまうこともあります。
民間・公営の賃貸住宅に住み続けるコストの問題
賃貸住宅に住み続けるときに、一番頭に浮かぶのが「家賃の問題」ではないでしょうか。近年では更新料や家賃の値上げなどの問題が、メディアで取り上げられることも少なくありません。しかし、資産や年金で将来的に家賃支払いへの心配がない場合には、賃貸住宅に住むこと、それ自体が大きなメリットであるかも知れません。
ただし、高齢を理由に入居を拒否される場合もあるようで、高齢になるほど選択肢が少なくなるのは仕方のないことなのでしょうか。
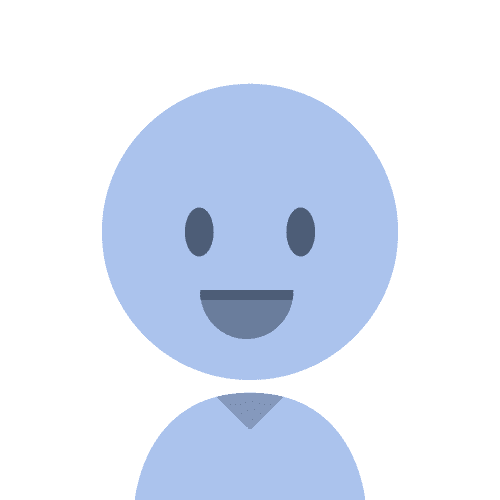
母が90歳を越えたときに、階段の無いところに引っ越しを計画しましたが、物件探しには苦労しました。結果的には、引っ越し自体が大変だと判断して断念しました。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは
サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)とは、バリアフリーが完備された高齢者の住まいです。入居すると、安否確認や生活相談のサービスが受けられるため、入居者が安心して暮らせる環境が整っています。
サ高住は、必要になったら外部のサービスを受けることも可能ですので「今のところ介護は必要ないが、将来の備えとして利用したい」という方におすすめです。
出典:みんなの介護

サ住高には、大きく分けて2つの種類があります。
一般型
要介護度が低く、自立して生活できることが条件で、介護サービスは外部のサービスを利用する。
介護型
要介護度が高くても入居可能で、介護サービスは常駐のスタッフから受けることができる。
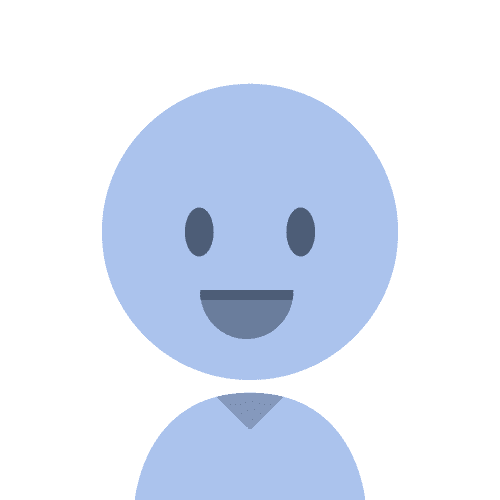
数年前、知り合いが両親のために「サ住高」を探していましたが、施設の種類や条件面が多種多様で、希望の物件に行きつくには時間がかかると言っていました。
老人健康保険施設という選択
いわゆる「老人ホーム」と言うことになりますが、終の棲家として誰にも迷惑をかけることもなく天寿を全うできることが、最大のメリットになると思います。しかし「自宅で最後を迎えたい」人のほうが多いと言うこともあるようですね。
PR
高齢者の一人暮らしが抱える問題とは

65歳以上の2割が一人暮らし
高齢者の一人暮らしは、年々確実に増えている傾向で、それに伴い「認知症の発症率上昇」や「孤独死」の問題も大きくなっています。そういう私自身も、このまま行くと一人暮らしになるのは確実だと思いますが、それに対して何かしようとか考えることはなかったと思います。
しかし、万一大きな病気になったり、孤独死になってしまった場合には「たくさんの人に迷惑をかけるのではないか?」という思いはありますね。
高齢者が一人暮らしになると、どうなる?
一人暮らしになると、初めに「生きがいが無くなった」と多くの人が感じるようです。元々、多趣味の人やスポーツをやっている人は出かけることが多く、人付き合いもあるでしょうから問題ないと思いますが、そうでない場合は急に一人になった孤独感から、そういう感情になるのは仕方のない事でしょう。
また、長期間一人暮らしをしている人であっても、加齢にともない「今まで出来たことが出来なくなった」場合や「体に不調がある日が多くなった」と感じると、将来への不安が大きくなると思います。
高齢者の一人暮らしを支えるもの
人の性格により、一人でいることを好んでいる場合もありますし、若い時から独身を貫いている人などは、一人暮らしが当たり前になっているので、一人でいることに慣れているのかも知れませんね。そんな人でも、病気になったりケガをしたりすると、誰かに頼りたくなることはあるでしょう。
日ごろから趣味や運動などを習慣づけることも良いとは思いますが、私は「誰かと会話することが少なくなる」ことが、一番問題だと思います。母は、おしゃべりなほうではないですが、以前私が仕事に行っているときに昼食ヘルパーさんが来ると、信じられないくらい、しゃべっているので驚くこともありました。
地域での見守りサービス
近年では、自治体や地域での「見守りサービス」を行っているところもあるようですね。特に地方の場合は、地域自体が広くなって対応するのに時間がかかったりすることがあり、地域全体でルールや体制を決めて、高齢者の見守りを行っています。
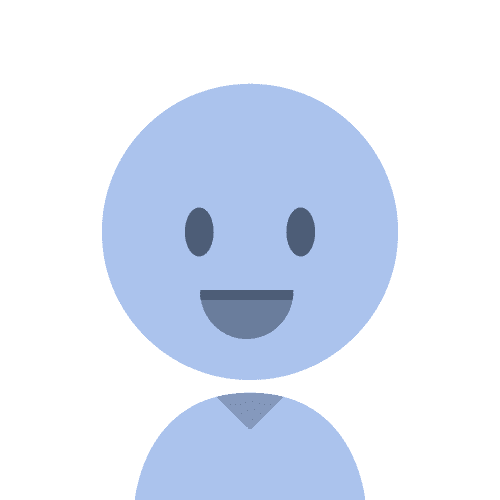
ある地域では、一人暮らしの高齢者宅で「薬は必ず冷蔵庫に入れる」などのルールを決めて、いつ誰が行っても、すぐに対応できるようにしていると聞いたことがあります。
高齢者の住宅問題は必ず大きな社会問題になる
「20●●年は、高齢者の住宅事情が大きな社会問題になる」と言う記事が、いつかは出ることは間違いないでしょう。特養ホームなどの空き待ちにともなう「介護難民」、高度経済成長期に建てられた大型団地の「老朽化と住民の超高齢化」、さらには一人暮らしの増加にともなう「孤独死」の問題など、高齢者にとっての住宅問題がひっ迫することは、すでに始まっているのかも知れません。
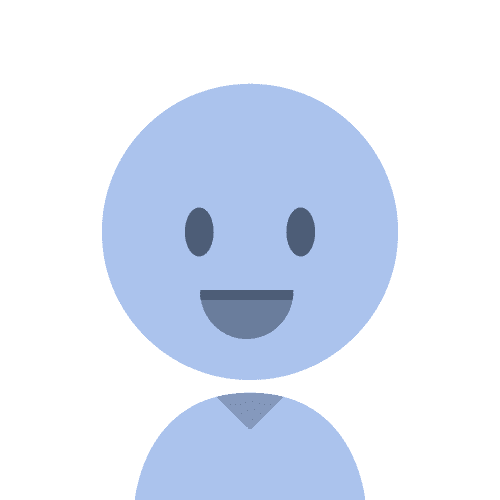
現在でも、エレベーターが無い昔の団地で、たくさんの高齢者が住み続けていると聞いたことがあります。行政も動いてはいるでしょうけど、高齢化のスピードの追いつけるのか、疑問が残りますね。