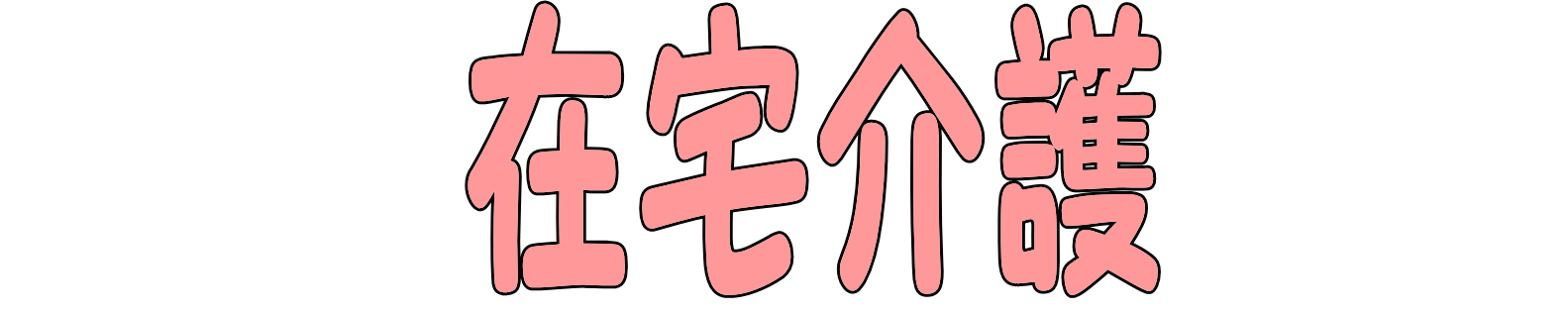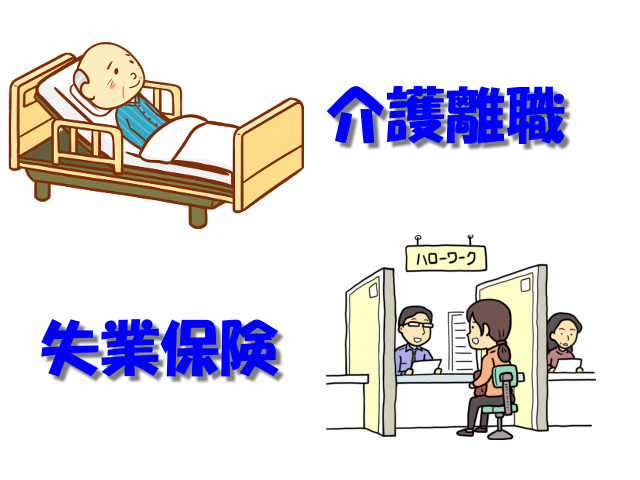介護離職問題と在宅介護の相関

厚生労働省が推進する在宅医療や在宅介護と介護離職の問題は、それぞれの問題に相関が発生するがゆえに、矛盾を感じる事もあります。仕事と介護の両立が出来れば、それに越したことはありませんが、家庭の事情により難しい場合もあります。
また、職場の制度や理解によって、介護休業や介護休暇の利用が、一律で行われていないのも現状で、今後は労働者と雇用をしている者との相互理解が進んでいくことが大事になるでしょう。
超高齢化社会へ向けて、行政の考え方とは
厚生労働省の在宅医療・介護推進とは
多くの国民が自宅等住み慣れた環境での療養を望んでいる。また、超高齢社会を迎え、医療機関や介護保険施設等の受入れにも限界が生じることが予測される。こうした中、在宅医療・介護を推進することにより、療養のあり方についての国民の希望に応えつつ、地域において慢性期・回復期の患者や要介護高齢者の療養の場を確保することが期待されている。
この資料の中で厚生労働省は、
- 国民の希望に応える療養の場の確保は、喫緊の問題。
- 「社会保障・税一体改革大綱」に沿って、病院・病床機能の分化・強化と連携、在宅医療の充実、重点化・効率化、地域包括ケアシステムの構築等を着実に実現していく必要があり、2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療・介護の実現に向けた策が必要。
と銘打って、
省内に「在宅医療・介護推進プロジェクトチーム」を設置し、在宅医療・介護を関係部局で一体的に推進
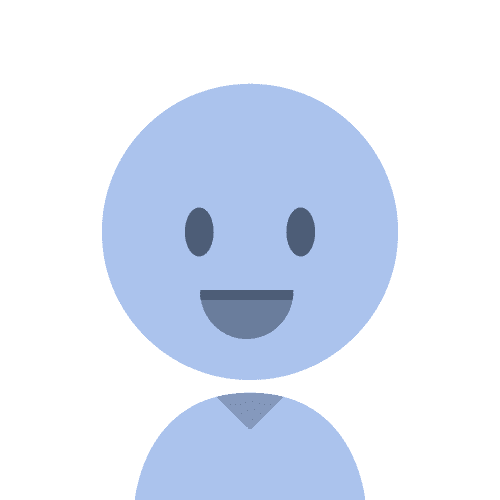
このように明記されていますが、一方では・・・
介護離職を防ぐための施策とは
高齢者人口の増加とともに、介護保険制度上の要支援・要介護認定者数は増加しており、今後、団塊世代が70歳代に突入することに伴いその傾向は続くことが見込まれます。介護者は、とりわけ働き盛り世代で、企業の中核を担う労働者であることが多く、企業において管理職として活躍する方や職責の重い仕事に従事する方も少なくありません。
そうした中、介護は育児と異なり突発的に問題が発生することや、介護を行う期間・方策も多種多様であることから、仕事と介護の両立が困難となることも考えられます。このため、厚生労働省では、育児・介護休業法に定められた介護休業制度などの周知徹底を図り、企業及び労働者の課題を把握し事例集を作成するなど、介護を行っている労働者の継続就業を促進しています。
そもそも少子高齢化で人口が減っていく中での人手不足に加えて、働き盛りの人たちが家族の介護のために離職してしまうと、日本の産業に大きなダメージが出るのは、火を見るよりも明らかです。
しかし、現実問題として「仕事と家族」が目の前にあるならば、家族が優先されるのは当然のことであり、その先にある問題とは相違することになりますね。
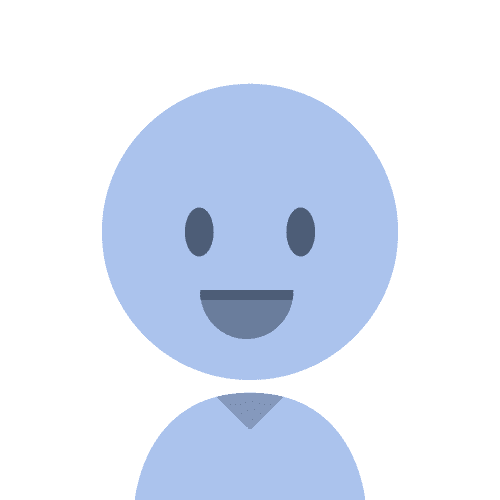
要するに「仕事はしながら、介護は自宅でお願いね」ということですね。しかし、結局は企業にお任せであり、法的な強制力はないので、現実的にはどうなんでしょうか。
介護の公的な制度とは誰のためにあるべきか
果たして国の政策や制度がアジャストして、「仕事と介護の両立」が機能する未来はあるのか。たしかに、それぞれの家庭で要介護度の違いや経済的な事、また、家族構成や住んでいる自治体が違うので、すべてを解決できることは少ないかも知れません。しかし、私が母の介護を通じて経験したことや、様々な人の話を聞いたり自分で調べたりしていると、いったいどうすれば良いのか、考えてしまうことがあります。

PR
仕事をしながら選べる介護サービスとは
家族がいつ介護が必要になるか分かりません。いざという時のために、仕事をしながら利用できる、主な介護サービスを見てみましょう。
※要介護度により、受けられるサービスの内容が変わる場合があります。
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。
通所介護(デイサービス)
通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、また、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。通所介護の施設(利用定員19人以上)に通い、利用者が有する能力に応じ生活機能の維持又は向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練等の利用者に応じた必要なサービスを通所介護施設の利用時間内において提供します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
短期入所生活介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
出典:厚生労働省「介護事業所・生活関連情報検索(介護サービス情報公開システム)」
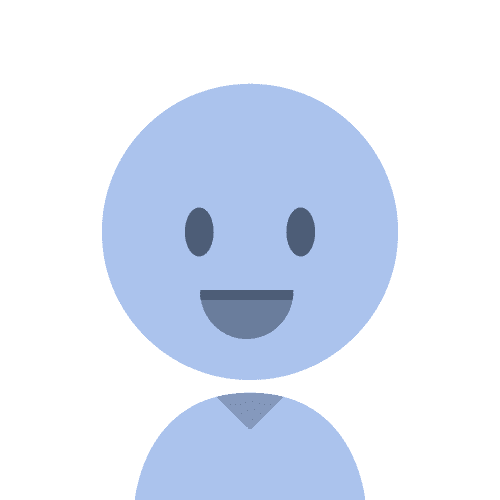
まだまだたくさんの介護サービスがあるので、リンクの厚生労働省ページで確認してみてくださいね。

将来のために介護の情報はとっても大事
私自身も、母親の介護が必要になるまでは、まったくと言って良いほど介護については無知であったと言えます。母が、70代後半で脳梗塞になったとき、念のため役所へ介護の相談に行くと、時代がまだ介護に追いついていなかったのか「介護が必要になってから来てくださいね」みたいなことを言われた記憶があります。
しかし、現在では地域包括支援センターやケアマネージャーが親切にフォローしてくれますので、何かあった場合には、先ず相談することが大切だと思います。