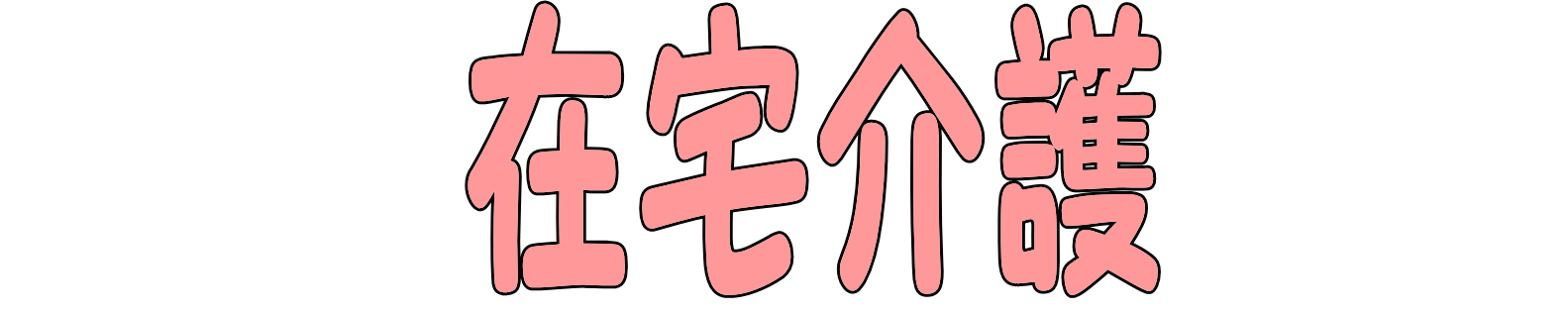家族介護者が抱える悩みと解決策を考える

家族介護者という言葉を聞くと、家族の一員を在宅介護している方々の強い責任感や、時には心の負担を感じている姿が思い浮かびます。私自身も、家族介護者に該当するわけであり、身体的だけではなく精神的にも疲弊することも少なくないと言えます。
しかし、それぞれの家族介護者が抱える悩みと言うのは、言葉に表される以上に根の深い部分が多いと言うのが現状です。そして、在宅介護における家族支援や具体的な施策については、これからの日本社会において、もっとも重要な取り組みが必要になると考えています。
私が母の介護をしていく上でも、常に心の中に置いている「家族介護者だからこそ大事なこと」を、自分自身の将来への教訓として、考え直してみたいと思います。
家族介護者支援の現状と課題について
厚生労働省が示す家族介護の支援とは
厚生労働省は「家族介護者支援マニュアル」という資料の中で、以下のような指針を打ちだしています。
家族介護者を「要介護者の家族介護力」として支援するだけでなく、「家族介護者の生活・人生」の質の向上に対しても支援する視点をもち、要介護者と共に家族介護者にも同等に相談支援の対象として関わり、共に自分らしい人生や安心した生活を送れるよう、地域包括支援センターの事業主体である市町村はもちろん、多機関専門職等と連携を図って、家族介護者にまで視野を広げ相談支援活動に取り組むこと。
要は、これまで要介護者の支援を中心に施策や制度を構築してきたが、これからは家族介護者の仕事や生活、或いは人生そのものを支援していくことも重要と言うことですね。例えば、家族介護者の支援目標として次のようなことを掲げています。
【これまでの家族介護者支援目標】
- 介護ストレスの緩和
- 地域での孤立防止
- 介護ノウハウの習得支援
- 地域見守りネットワーク支援 等
【今後充実をはかるべき家族介護者支援目標】
- 仕事を始めとする社会参加の継続維持
- 生活及び人生の質の充実維持の確保
- 心身の健康維持・充実
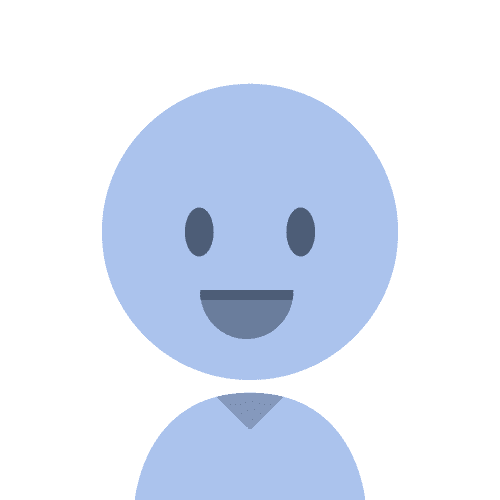
とは言え、介護離職者が年間10万人という中で、具体的な支援策は出てくるのでしょうか。
家族介護者の精神的なストレスが介護離職につながる
「仕事と介護の両立に関する労働者調査」によると、介護離職した人の離職理由として、「自分の心身の健康状態悪化」が一番多かったとのデータがあります。これについては、私自身が経験したことでもありますが、身体的な苦痛はある程度我慢できますが、心の健康状態が悪化すると、「まず、何かを捨てないと必ず行き詰まる」との思いが強くなります。そうなると、最初に「捨ててしまっても後で何とか出来るかも」と言う観点から、離職を選んでしまうのではないでしょうか。
しかし、実際には「収入が無くなる」「社会との繋がりが薄れる」「要介護者への不満が大きくなる」など、何とも出来ない現実が大きく立ちはだかってくるのは間違いないと思います。まず、離職する前に心身ともにケアが出来るシステムを構築しないと、この介護離職の波を止めることは出来ないかも知れません。
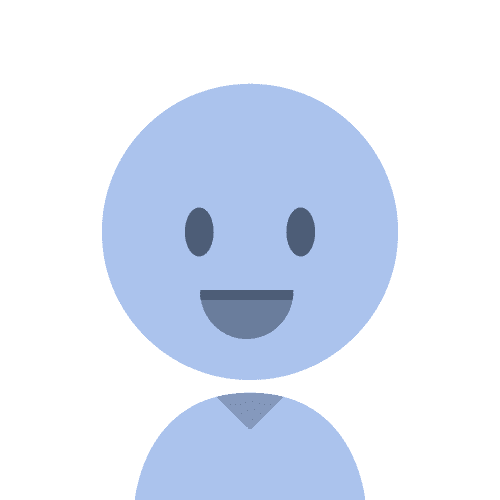
しかし、それぞれの仕事場や働き方によって課題の幅は大きく、一律で支援できる制度の構築は「いばらの道」と言えます。


PR
家族介護者の支援は地域とコミュニティから
介護で疲弊する前に、心のケアが必要になる
在宅介護での、家族介護者が抱えるストレスを軽減するためには、専用のストレスケアプログラムで、定期的なカウンセリングや、グループでのサポートを設けることが、精神的なサポートになるでしょう。
また、介護者向けのコミュニティやリラクゼーションなどのサービスを受けるなどのことも、ストレス軽減に役立つのではないでしょうか。しかし、このような取り組みは、個人の力ですぐに出来るものではないと思いますので、地域全体で支え合いながら、公的な支援が進んで行くことを望むばかりです。
SNSや社内支援システムなどを利用して、寄り添う支援を
大手企業などは、すでに「社内介護支援システム」などで介護離職を防ぐ対策に乗り出していますが、私自身、以前の職場でもそういう案内が「イントラネット」にありました。ただ、私は派遣社員であったこと(派遣社員でも利用はできる)や自分に任された仕事環境など考えて、利用することはありませんでした。この点については、自分勝手な判断だったかも知れませんが、「そういう雰囲気」だったことは間違いありません。
そういう意味では、SNSなどを利用して「支援の輪」が広がっていくのは非常に良いことだと思います。ネットなどで調べてみると、すでに介護者などのコミュニティや支援の手を差し伸べる場が見られますね。
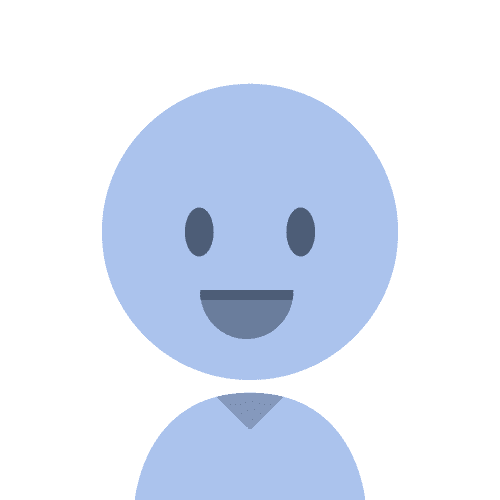
SNSは、いろんな意味で表裏一体な部分が多いと思いますので、逆にストレスにならないように気を付けたいですね。

介護者の悩みは、必ず誰かが助けてくれる
私も含めて、家族介護者の人たちが大切にしたいことは、「必ず誰かが助けてくれる」という気持ちを持つことだと思います。心のこと、健康のこと、お金のことなど、何でも誰かに相談することができれば、道は開けると思います。
以前、母が足が痛くて歩けないと言って病院にいきたかったのですが、その時はまだ我が家に車椅子がなかったのでケアマネージャーに相談してみました。そうすると、「地域包括支援センターに借りれる車椅子があるかも」と言われて行ってみたら、たまたま出払っていて借りれなかったのですが、その支援センターの人が、近くの老人介護施設に連絡してくれて、レンタル用の車椅子を借りることができました。
この時は、非常に助かりましたので「先ずは誰かに相談する」ことの大切さを痛感しました。今後は、ネットやAIの力で、すぐに相談できて的確なアドバイスがもらえるようなシステムができれば良いですね。