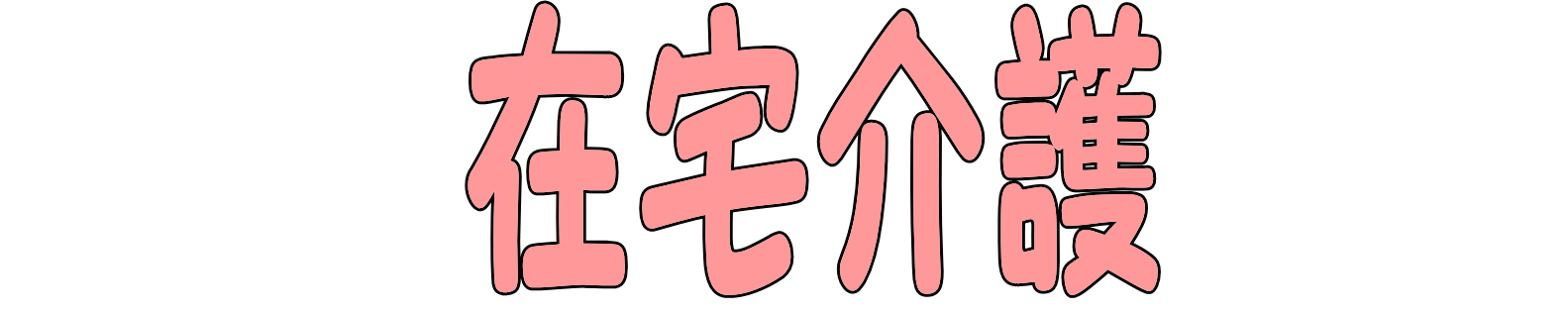老老介護の実態と社会的背景を考える

老老介護は、近年ますます注目される重要な問題となっています。特に超高齢化社会が進んでいるなかで、高齢者同士が互いに介護を担う状況が広がっている背景には、様々な要因が影響していると言えますが、介護に対する経験や知識が不足していることが多く、家族同士の負担が大きくなることが少なくありません。
私自身も、まだ60代前半とは言え、老老介護の初期段階と言える状況ではありますので、母の在宅介護に対して、年々さまざまな負担がかかってくることは、日々の生活の中で感じています。今後、社会がこの問題に対して前向きになり、制度や支援が充実していくことを心から願っています。
老老介護の実態と増えている理由
老々介護とはどのような状況?
「老老介護」とは、介護者と被介護者がどちらも65歳以上の高齢者となっている状態のことです。夫婦や親子、兄弟など、その構成はさまざま。75歳を超えている方同士の場合は「超老老介護」と言われています。
日本では老年人口である65歳以上の高齢者が全人口の25%を超え、4人に1人が高齢者という状況です。それに伴い、老老介護・超老老介護も増加しています。
出典:みんなの介護

老老介護が増加している社会的背景とは?
老老介護が増加している要因は、平均寿命の延伸と少子高齢化の進行の一言だと言えます。そして、介護を担う世代が減少していくなか、高齢者が高齢者を支え合うという構造が生まれ、また、経済的な理由から介護サービスの利用が難しい場合や、家族との距離が離れた場合もこの状況を助長しているではないでしょうか。さらに、介護に関する情報が不足していることや、制度的な支援が十分ではない状況も影響しているかも知れません。
老老介護の割合はどれくらい?
老老介護は年々増加傾向にあると言われており、在宅介護の家庭では「65歳以上同士が50%以上、75歳以上同士が30%以上」であるとされています。今後は、介護を受ける側も支える側も、年齢が更に上がるという現象が見られ、将来的には、これがより顕著になることは間違いないでしょう。
介護をする側とされる側の年齢差の違い
若い世代の人にとって、親の介護や老老介護は「まだまだ先の話」だと思います。しかし、将来必ずやってくるであろう家族の介護について、今のうちから考えておくことは、けっして時間の無駄とは言えません。ここでは、もし親との年齢差により、介護の未来がどうなるかを考えてみましょう。
両親との年齢差が25歳の場合
この場合、親が要介護になる可能性がある75歳になったとき、子供が50歳であり、働き盛りで管理職になっていることも多いと思います。もし、ここで両親の介護が必要になると、仕事に影響が出ることは避けられないでしょう。
また、親が90歳まで長生きしてくれたら子供は65歳なので、まさに老老介護と言える状況になりますね。この年齢差の人については「親が70歳、子供が45歳になったら介護予防の備え」を考えてみてはいかがでしょうか。
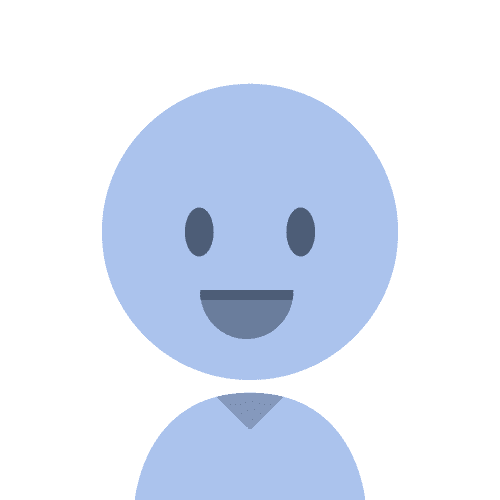
でも、今の70歳くらいなら元気な人が多いので「まだまだ、そんな年齢にはなってない!」と言って、怒られるかも知れませんね。
両親との年齢差が40歳の場合
この場合、親が要介護になる可能性がある75歳になったとき、子供はまだ35歳であり、社会人としてもこれからまだまだ頑張れる年齢でもありますね。もし、ここで両親の介護が必要になると、仕事に影響が出ることはもちろん、自分の将来像も変わってしまうかも知れません。
また、親が90歳まで長生きしてくれた場合は、子供がまだ50歳なので、まさに働き盛りで介護離職になる可能性が高くなってしまいます。この年齢差の人については「親が70歳、子供が30歳になったら介護予防の備え」をすることを考えなければいけませんが、実際にはそこまで考える人は少ないでしょう。
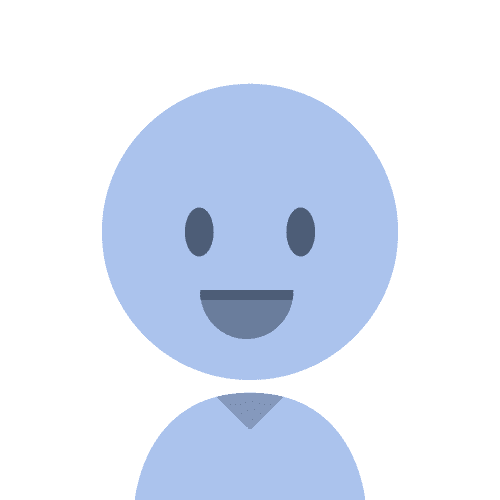
私の場合、32歳差になりますが、母が70歳の時には全くと言って良いほど、将来の介護のなど頭になかったですね。むしろ、自分のことで精一杯だったと思います。

PR

老老介護における問題の解決策と支援の方向性
地域包括支援センターが果たす役割
地域包括支援センターは、高齢者が自立した生活を営むための支援を行っている重要な存在です。具体的には、介護サービスに関する情報提供や相談を行い、地域でのネットワーク作りを促進し、高齢者が安心して生活できるようになることが期待されています。地域包括支援センターが整備されることで、孤立している高齢者やその家族へ手を差し伸べることができ、老老介護の負担軽減に大いに貢献してくると考えられています。
介護者の負担軽減に向けた具体的な解決策
老老介護を行う側の負担を軽減するためには、いくつかの具体的な解決策が考えられます。まずは、介護サービスの積極的な利用をすることですが、訪問介護やデイサービスなどは、介護者自身の心身の健康も守ることができます。また、家族間でのコミュニケーションやサポート体制を整えることで、介護者が感じる孤立感を軽減していくことも重要な要素なのではないでしょうか。
共倒れを防ぐために考えるべきこと
老老介護において、大きなリスクがあるとすれば「共倒れ」と言うことになるでしょう。特に高齢者同士で介護を行う場合、どちらか一方が健康を崩すことが多く、その結果として全体の介護が機能しなくなる可能性があります。これを防ぐためには、介護サービスの利用はもとより、家族内でも介護の負担を分散することが大切です。さらに、健康診断やケアマネージャーとの連携を通じて、定期的に状況を見直すことも共倒れを防ぐことになります。
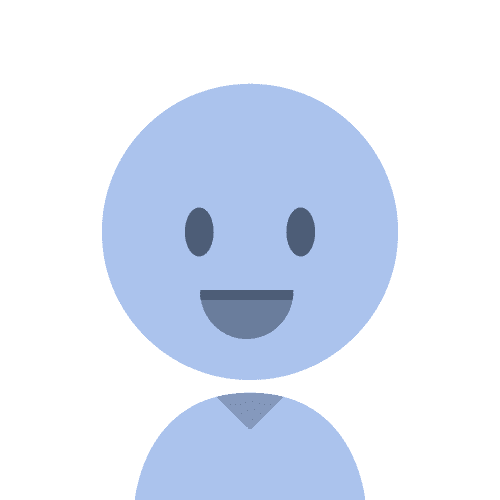
それぞれの家庭により、家族構成や地域の差があるので、解決策と言ってもすぐに機能できるものは少ないかも知れません。しかし、家族と地域、ケアマネージャーがお互いに情報を共有することによって、解決できる問題があるかも知れませんね。